赤外線観測で調べたオウムアムアの特性
【2018年11月20日 NASA JPL】
2017年10月に米・ハワイのパンスターズ望遠鏡で発見された史上初の恒星間天体「オウムアムア」(1I/2017 U1)は、発見直後から世界中の望遠鏡やハッブル宇宙望遠鏡で観測が行われ、大きさや特徴などが調べられてきた。可視光線波長での明るさが大きく変化することから、オウムアムアはおそらく細長い形をしており、長径が800mほどだろうとみられている。

オウムアムアの想像イラスト(提供:European Southern Observatory / M. Kornmesser)
その後、オウムアムアの運動の様子を調べた研究から、オウムアムアは彗星のように凍ったガスでできており、太陽へ接近した際に表面からガスが放出した影響でオウムアムアがわずかに加速したらしいという結果が発表されている(参照:「やっぱり彗星?予想外の加速を受けるオウムアムア」)。この結論は、オウムアムアが典型的な彗星よりも小さいという見積もりに依存している。
2017年11月、NASAの赤外線天文衛星「スピッツァー」もオウムアムアに向けられた。赤外線の観測では、可視光線波長の観測に比べて、より具体的に天体の大きさを知ることができるのだが、残念ながらすでにオウムアムアはスピッツァーで観測するには暗くなってしまっていた。しかし「スピッツァーでは見えなかった」という結果自体が非常に価値のあるもので、オウムアムアの大きさの上限を推定することが可能となった。
この結果をもとに、米・アリゾナ大学のDavid Trillingさんたちはモデル計算を行い、オウムアムアの大きさが100~400mであると推測した。この場合の大きさは「オウムアムアが球形をしている」と仮定したものであり、明るさの変化から推定されるような細長い形状の場合は長径が240~1080mに相当する。この大きさは、オウムアムアの加速運動やガス放出活動からの見積もりサイズと矛盾しないものだ。
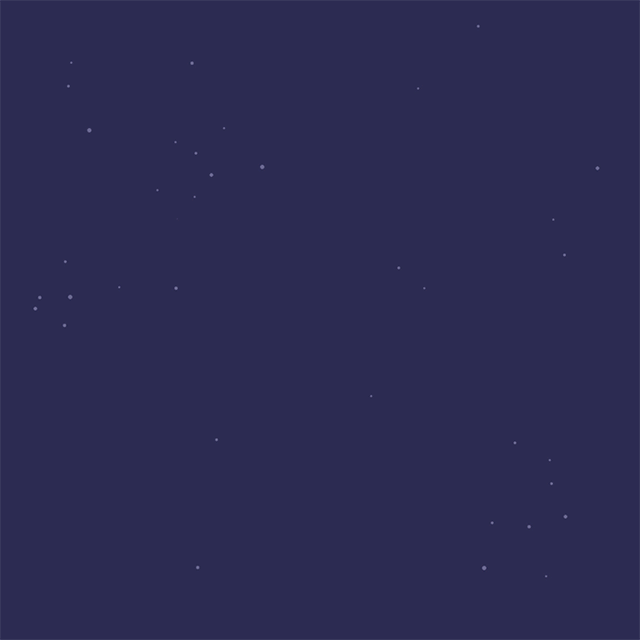
オウムアムアがガスの放出でわずかに加速する様子を表すアニメーション動画(提供:NASA/JPL-Caltech)
また、Trillingさんたちは、オウムアムアの表面のアルベド(反射率)が彗星の10倍ほども高い可能性があることも示している。
オウムアムアは、恒星から遠く離れて数百万年間も恒星間空間を旅してきたため、星の熱に暖められて新鮮な表面が露出することがなかった。しかし、発見される約5週間前に太陽に接近したことにより、オウムアムアでガスの放出が起こり、新鮮な表面が露出したのかもしれない。そして、表面の塵や汚れが取り払われたり、ガスが反射率の高い氷や雪で表面を覆ったりした結果、オウムアムアの表面のアルベドが高くなった可能性があるという。
発見から1年、オウムアムアは現在、土星軌道ほどまで遠ざかってしまった。そして二度と、太陽系の内側に戻ってくることはない。
〈参照〉
- NASA JPL:NASA Learns More About Interstellar Visitor 'Oumuamua
- Astronomical Journal:Spitzer Observations of Interstellar Object 1I/'Oumuamua 論文
〈関連リンク〉
関連記事
- 2020/08/24 恒星間天体オウムアムアは水素製ではない
- 2020/07/15 リュウグウは炭素が多く黒い小惑星
- 2020/01/24 オウムアムアやボリソフ彗星の起源は太陽系外
- 2018/10/02 ガイアが明かすオウムアムアの故郷
- 2018/07/02 やっぱり彗星?予想外の加速を受けるオウムアムア
- 2018/04/02 オウムアムアは巨大惑星に破壊された彗星かもしれない
- 2018/03/23 オウムアムアの故郷は連星系
- 2017/12/25 オウムアムアは「厚い有機物で覆われた雪玉」か
- 2017/11/24 恒星間天体「オウムアムア」は細長い葉巻形
- 2017/11/07 観測史上初の恒星間天体、名前は「ʻOumuamua」











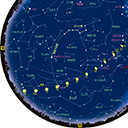
![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)