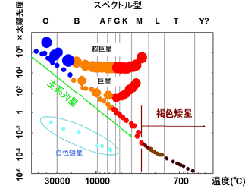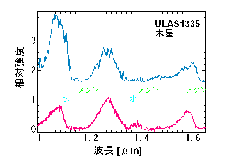恒星と惑星をつなぐ「もっとも低温の星」発見
【2008年9月11日 国立天文台】
単独で生まれるものの、規模が小さすぎて核反応が続かない星・褐色矮星。この、惑星と恒星をつなぐ貴重な天体を、日英等の研究グループが次々と発見した。その中には摂氏280度と、惑星以外ではもっとも冷たい星も含まれる。
さまざまな恒星の温度と光度の関係を示したヘルツシュプルング・ラッセル(HR)図。クリックで拡大(提供:国立天文台)
発見されたもっとも低温のT型星「ULAS1335」の赤外線スペクトル(赤色)と木星のスペクトル(水色)を示した図。クリックで拡大(提供:国立天文台)
ULAS1335の赤外線画像。クリックで拡大(提供:国立天文台)
恒星の性質で重要なのは、質量と温度だ。質量が大きいほど恒星の温度も高くなり、色も赤から黄、白、青というように変わっていく。例えば太陽の表面温度は摂氏約5,500度で黄色っぽい色をしているが、質量が15倍の星なら約29,000度で青く、半分なら約3,600度で赤くなる。
このうち色に注目して恒星を分類したのが「ハーバード分類」だ。恒星が放つ光のスペクトルに応じて、青いO型(最高で5万度に対応)から順にB、F、G、Kと続き、最後は赤いM型(最低で2,200度)である。ところが、1980年代後半から、M型よりもさらに低温の星が見つかるようになり、2,200〜1,100度に対応する「L型」と1,100〜400度に対応する「T型」が分類に加わることになった。
L型の一部やT型の星はあまりにも小さく温度が低いため、水素の核融合反応を持続させることができず、ふつうの星(恒星)のように輝くことができない。その境界は太陽質量の約7.5%であり、これより小さい星は「褐色矮星」と呼ばれる。恒星の周囲に誕生する惑星と違って、褐色矮星は単独あるいは似た質量の天体とともに星間物質の中から誕生する。太陽質量の約1.3%(木星の約13倍)以上の天体では一時期だけ特殊な核融合反応が起きるため、一般にこれが惑星と褐色矮星の境界とされている。
このように恒星と惑星の中間的存在と言える褐色矮星だが、その性質は恒星や惑星について知る上でも重要な手がかりとなる。例えば、恒星のすぐ近くをまわる系外惑星の大気を観測するのは困難だが、褐色矮星は表面温度が近い上に、直接スペクトルを観測できる。つまり、低温の褐色矮星を観測することによって、系外惑星の大気について推定することが可能なのだ。
しかし、褐色矮星は可視光で見るとひじょうに暗く、予想される存在数も少ないため、広い領域を深く探査しなければならない。
国立天文台の田村元秀准教授が率いる日英等の研究チームは、「UKIDSS/LAS-ユーキッズ・広域サーベイ」のデータの一部から褐色矮星の候補天体を探した。このサーベイは、英国の口径3.8メートル赤外線望遠鏡UKIRTを使い、4,000平方度という広い領域について従来より3等級も暗い赤外線天体を探査するものである。
見つけ出した天体のスペクトルから大気温度を推定した結果、これまでに28個ものT型星を発見した。このうち5個の星の温度は、従来の最低記録をさらに下回るものだった。おとめ座の方向約30光年の距離にあるULAS1335は、推定温度がわずか280度。惑星以外の星としてはもっとも低いのはもちろん、太陽系の惑星である水星(昼側)や金星よりも冷たい。
これまで知られていたT型星は約100個だったが、田村准教授らはUKIDSSの観測開始からわずか3年で28個も発見したことになる。さらに捜索範囲を広げることで、最終的に数百のT型星が見つかると期待されている。さらに冷たい星が見つかる可能性もありそうだ。今回見つかった星を含め、今後の研究の進展に熱い期待がかかる。
この研究は、9月11日〜13日に岡山理科大学で開催される日本天文学会の秋季年会の記者会見で発表された。