『明月記』の記録などから解明、平安・鎌倉時代の連発巨大磁気嵐の発生パターン
【2017年3月23日 国立極地研究所】
太陽活動が激しくなり大きな磁気嵐が発生すると、日本のような緯度の高くない地域でもオーロラが観測されることがある。2003年10月には北海道から東北、中部地方あたりでこうした「低緯度オーロラ」が観測され、2015年3月にも北海道で低緯度オーロラが見られた。

2003年10月29日に北海道で見られたオーロラ(撮影:津田浩之さん(陸別天体観測所))。クリックで投稿画像ギャラリーのページへ
1週間のうちに何晩も緯度の低い地域でオーロラが観測される「長引く赤いオーロラ」の記録として、これまでに調査されている中で日本最古のものは、鎌倉時代に藤原定家が著した『明月記』にある。1204年2月21日、京都の夜空に「赤気」(オーロラの意)が現れて恐ろしい様子だという記述が残されており、2月23日にも再び「赤気」が出現したと記されている。また、『御室相承記』(おむろそうしょうき、鎌倉時代の作品)にも、2月21日から23日まで「赤気」が現れ高野山参詣をとりやめたという記述があり、京都で複数の目撃例が残っていたことになる。
国立極地研究所の片岡龍峰さんたちの研究グループは、中国の歴史書『宋史』に、2月21日に太陽に特に大きな黒点が現れたという記述を見出した。これらの古典籍の記述を現代的な観測データから推定すると、太陽から噴き出たコロナ質量放出が何度も地球に直撃し、大きな磁気嵐が繰り返し発生する「連発巨大磁気嵐」が起こっていたと考えられる。
過去2000年の京都の磁気緯度(自転軸ではなく地磁気の軸を基準とした緯度)を計算したところ、1200年頃は地磁気の軸が現在とは逆に日本のほうへ傾いていたため、過去2000年間で日本からオーロラが最も観測しやすい時期であったこともわかった。定家が記した「赤気」は見間違いではなく、確かに太陽の異常を反映して京都の空にオーロラが現れていたことが、科学的に追究され確かめられたことになる。
さらに時代を遡って連発巨大磁気嵐の発生パターンを検討するため、片岡さんたちは『宋史』における900年代~1200年代の「長引く赤いオーロラ」の記録と、太陽活動の強弱を反映する樹木の年輪の炭素同位体比の測定データを比較した。その結果、太陽活動の極小期前後よりも極大期付近に多く記録が残されていたこと、太陽活動が長期的に弱くなった1010~1050年には「長引く赤いオーロラ」の記述がないことが明らかになった。
今回の成果は、『明月記』『宋史』に残された人文的な営みと年輪に残された太陽活動のリズムという自然科学とを総合的に組み合わせ協力研究して得られたものだ。将来への応用として科学的には、今後起こりうる最悪の宇宙環境を理解、予測し、大規模な停電や通信障害、人工衛星の故障といった「宇宙災害」への具体的な対策を立てる上で重要なものとなる。また、人文学的側面としては、過去の宇宙環境が解明されることで古典籍の読み方も変わり、当時の人々の天文観へのより深い理解に役立つことが期待される。

2016年3月に開催された「古典オーロラハンター」ワークショップの様子(星ナビ2016年6月号掲載)。古典籍からオーロラの記述を探している(撮影:梅本真由美)
〈参照〉
- 国立極地研究所: 『明月記』と『宋史』の記述から、平安・鎌倉時代における連発巨大磁気嵐の発生パターンを解明
- Space Weather: Historical space weather monitoring of prolonged aurora activities in Japan and in China 論文
〈関連リンク〉
- 国立極地研究所: http://www.nipr.ac.jp/
- AURORA 4D PROJECT: https://aurora4d.jp/ 「オーロラと人間社会の過去・現在・未来」
- アストロアーツ:
- 「星ナビ」2016年6月号 「最先端の研究に参加しましょ!古典オーロラハンター体験記」(連載「天文台マダムがゆく」)
- 投稿画像ギャラリー: 低緯度オーロラ:
関連記事
- 2024/12/13 日本で撮影された青い低緯度オーロラの出現場所を推定
- 2024/11/06 今年5月に日本で見られた低緯度オーロラは高高度、色の謎も解明
- 2024/05/13 日本など各地で低緯度オーロラを観測
- 2023/05/02 日本の歴史資料から読み解く太陽活動の周期性
- 2021/12/24 1957-8年、太陽活動が観測史上最大級の時期のオーロラ国内観測記録
- 2021/09/13 過去3000年のオーロラ出現地域を計算、文献とも一致
- 2019/07/30 地球大気の流出量は磁気嵐のタイプによって異なる
- 2019/05/23 60年前の扇形オーロラと巨大磁気嵐の関連
- 2019/03/20 日本天文遺産に「明月記」と福島県「会津日新館天文台跡」を認定
- 2017/09/22 江戸時代の古典籍に記録が残る史上最大の磁気嵐
- 2017/09/07 11年ぶり、最強クラスの太陽フレアが発生
- 2016/07/27 オーロラエネルギー取り込みの仕組みを衛星観測で解明
- 2015/07/17 太陽風の玉突き事故で起こった大規模磁気嵐
- 2015/03/19 北海道で11年ぶりにオーロラを観測
- 2014/10/14 「明月記」の超新星記録を世界に紹介した射場保昭
- 2010/12/09 何の予兆もなく起こる、太陽による高エネルギー粒子大放出
- 2010/08/12 南極の昭和基地の全天カメラがとらえたオーロラ
- 2010/08/04 太陽表面の地球側でコロナ質量放出、北米や欧州などで低緯度オーロラが出現か
- 2010/03/19 太陽フレアをほぼ再現、最新モデルの開発成功
- 2010/01/26 太陽フレア予報の鍵は、ねじれる磁場











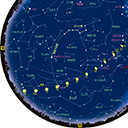
![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)