衝突加熱で容易に消去される、隕石の記憶
【2018年2月1日 東京工業大学】
地球に落ちてくる隕石の多くは、火星と木星の間に広がる小惑星帯を起源としていることが、成分や軌道の分析から明らかになっている。
![小惑星帯と準惑星「ケレス」のイラスト] 小惑星帯と準惑星「ケレス」のイラスト](/article/attachment/10599/belt.jpg)
小惑星帯と、小惑星帯最大の天体である準惑星「ケレス」(右下)のイラスト(提供:ESA/ATG medialab)
こうした隕石に記録された放射壊変年代「アルゴン年代」は、隕石の母天体が1000K(摂氏約700度)の高温にさらされた時刻を示す指標となる。多くの隕石は初期の太陽系で母天体が冷え固まった時刻、つまり約45~46億年前の年代を示すが、一部のものは若い年代を示す。
母天体を1000Kまで加熱する過程は天体衝突しか考えられないことから、若い年代を示す隕石群の年代頻度がどのように時間変化するかは太陽系天体の衝突史とみなすことができる。この変化は初期太陽系の研究における一つの制約条件として利用されてきた。
アルゴン年代から衝突史の情報を引き出すためには、どの程度の衝突速度の場合に母天体が1000Kまで加熱されるかという「アルゴン年代消去衝突速度」を知る必要があり、過去の理論的研究によれば秒速6~8kmという高速衝突だと推定されてきた。これは小惑星帯における典型的な衝突速度(秒速約5km)よりも高速である。
ところが、近年の衝突実験や数値計算から、現実の物質の場合は推定よりも低速度の衝突でも大きな加熱度が達成されることがわかるようになってきた。低速の衝突でもアルゴン年代消去が起こるとすれば、アルゴン年代から復元される初期太陽系の姿は大幅に塗り替えられる可能性がある。
千葉工業大学の黒澤耕介さんと東京工業大学の玄田英典さんは数値衝突計算を行って、現実の岩石の弾塑性体の挙動を計算に取り入れた場合の加熱度を調べた。
すると、衝撃波の伝播で圧縮・破砕された岩石が膨張して減圧する際に内部摩擦や塑性変形によって追加発熱が起こり、秒速2kmという低速度衝突の場合でも衝突天体質量の10%が1000Kまで加熱されることが明らかになった。つまり、秒速6~8kmと考えられていたアルゴン年代消去衝突速度は、実際には秒速2kmだったことになる。
![数値計算結果の例] 数値計算結果の例](/article/attachment/10598/result.jpg)
数値計算結果の例。(上2つ)(a、b)は衝突後のある時刻のスナップショット。(下2つ)(c、d)は(a、b)で示した計算中の温度-圧力の時間変化(提供:東京工業大学のリリースページより)
今回の結果は、隕石のふるさとである小惑星帯の典型的な衝突でも追加加熱によってアルゴン年代消去が起こることを示すものであり、初期太陽系の衝突環境は従来の推定よりも穏やかであったことを示唆する成果となった。
〈参照〉
- 東京工業大学:隕石の記憶は容易に消去される - 天体衝突時の加熱過程における物質強度の効果を解明
- Geophysical Research Letters:Effects of friction and plastic deformation in shock-comminuted damaged rocks on impact heating 論文
関連記事
- 2023/12/15 リュウグウの岩石試料が始原的な隕石より黒いわけ
- 2023/04/03 木星と土星の共鳴が鍵、地球型惑星と小惑星帯形成の統一シナリオ
- 2023/02/27 リュウグウの始原的物質は太陽系で最初期にできたものかも
- 2023/02/20 南極隕石が明らかにした月の火山活動の変化
- 2023/01/18 隕石の有機物が物語る過去の火星環境
- 2022/12/14 隕石のアミノ酸はガンマ線で作られた可能性
- 2022/11/04 火星で観測史上最大の天体衝突
- 2022/10/25 リュウグウ粒子からガス成分を検出
- 2022/04/21 衝突の記憶を刻む小惑星由来の隕石
- 2022/03/18 ドローンとAIで隕石を発見
- 2022/03/17 ケレスに衝突した隕石の大きさと数の謎
- 2022/01/31 アンモニア含有鉱物が示す小惑星の大移動
- 2021/11/15 地球の大気・海水の量は小惑星の大量衝突で決まった
- 2021/08/17 隕石の「磁気の記憶」から読み解く、太陽系初期の歴史
- 2021/08/03 太陽系外縁から移動してきた?小惑星帯に非常に赤い天体
- 2021/07/21 天体衝突が残す鉱石、わずか1億分の1秒で生成
- 2021/05/11 小惑星での有機物生成を再現する実験
- 2021/04/30 二酸化炭素が豊富な水を隕石中に初めて発見
- 2021/02/01 隕石から新鉱物「ポワリエライト」を発見
- 2021/01/26 太陽系で最古の水の証拠、隕石から検出











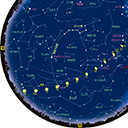
![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](https://www.astroarts.co.jp/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)