火星の大気は過飽和? 予想以上の水蒸気が存在する可能性
【2011年10月7日 ヨーロッパ宇宙機関】
ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の火星探査機「マーズエクスプレス」が火星大気の高度ごとの水蒸気の分布の観測を行った。その結果、火星大気は季節によっては過飽和と呼ばれる状態になっており、これまでの見積もりより10〜100倍程度多い水蒸気が大気に存在していることがわかった。
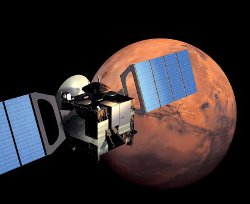
「マーズエクスプレス」と火星のイメージ(提供:ESA Illustration by Medialab)
火星表面から宇宙空間までの水分子の動き。太陽光によって地表面の水が蒸発し、一部は雲として取り込まれる。さらに太陽光の紫外線によって光解離を起こしたものは水素原子と酸素分子に分解され、宇宙空間へと逃げていく。クリックで拡大(提供:ESA/AOES Medialab)
火星は地球に約2年に1度の頻度で接近する。そのたびに探査機が打ち上げられ、これまでに多くの探査機が火星を調査してきた。しかし、これらの探査機の多くは、火星の地表面の様子や水平方向の違いを知ろうとするものが多く、特に水蒸気の鉛直方向(高度ごと)の分布を調べる探査は行われていなかった。
ESAの火星探査機「マーズエクスプレス」は、分光装置「SPICAM」を用いて日の出と日の入りのタイミングで観測を行い、水蒸気の鉛直方向の分布を求めることに成功した。
火星大気の水蒸気は地球の約1万分の1と非常に少量しか存在していないが、もっとも季節変動の激しい気体の1つだ。ダイナミックに動く微量気体であり、大気の構造や火星の水循環を調べる上で、水蒸気の鉛直方向の分布は非常に重要な情報であった。
通常、地球の大気では温度が下がると共に水蒸気が飽和点を越えると、大気中のダストやエアロゾル、塩などの周りに水がくっついて液体または氷の状態になってしまう。ダストやエアロゾルなどが非常に少ない環境では水蒸気が液体になることができず、飽和状態を超えても水蒸気として存在し続けることがあり、これを過飽和と呼ぶ。
火星の北半球が春と夏になった頃、驚くべき観測結果が得られた。なんと火星大気の水蒸気が過飽和状態になっていたのだ。これまで火星の大気は非常に温度が低いため、水蒸気が飽和点に達したときには氷になってしまうと考えられてきたが、SPICAMの結果によれば高度50km程度の中間層では、遠日点の辺りでしばしば過飽和状態になっていることがわかった。
この過飽和状態は地球の10倍もの規模で起こっており、これまでのモデルでは高度20〜50kmに存在している水蒸気量を10〜100倍程度も少なく見積もっていたことがわかった。この結果はこれまでのモデルの書き直しを迫ると共に、より多くの水が光解離(注)を起こす高度まで運ばれていることを示している。
光解離を起こした水は宇宙空間へと逃げていくため、今回の観測結果は火星の水がどの程度逃げたのかという議論と深く関わってくる。またこの発見は、惑星規模の気候変動や水循環の解明についても大きな影響を与えるだろう。
今回の結果は、火星で砂嵐(ダストストーム)が発生していない、ダストのない時期に得られたものだ。ダストがない状態であれば、10km以下の構造を捉えることができるが、ダストストームが発生した南半球が夏の時期には水蒸気を形成する核となるエアロゾルやダストが大量に大気中に供給されたため、過飽和はほとんど見ることができなかった。
注:「光解離」 分子が太陽光の紫外線を受けて、原子や分子に分解されることを指す。水蒸気の場合は光解離によって水素原子や酸素原子に分解される。











